背景の記憶(240)
父の死後、兄と姉が相次いで亡くなり
ついに・・・独り
六人兄弟の末っ子
実母は三歳の時、病死(破傷風)
三人の兄と姉は幼くして病死
残った兄と姉は早くから家を出たため、一人っ子のようなもの
そういう自分も16歳で家を出て・・・
まさしく〜さすらい人の子守歌(旧web版 Ne'o activity)

背景の記憶(239)
終業のチャイムが鳴ったのは、
アルバイトの僕が、丁度車の車庫入れを終えた時だった。
そして、君も作業を終えて作業場から出てきた。
僕には気づかず、ちょっと背伸びをしてから、
後ろに束ねていた長い髪をほどいた。
さらさらの黒髪が、肩に扇のように広がった。
やがて気配を感じて振り向いた君は、
これまでになく大人びて見えて、
僕はハッと息をのんだ。

背景の記憶(238)
あまりにストレートすぎて
戸惑った僕
どこまでが本意なのかつかみきれなくて
一喜一憂した僕
そんな僕の心の変動を楽しんでいるかに見えたのに
完璧な心変わりと感じ取ってしまった君
その場しのぎの言い訳や説明がいやで
沈黙の穴倉に潜り込んだ僕
それがまた不信に輪をかけて
僕は崖っぷちに追い込まれてしまったのだった
言葉の無力と沈黙の怖さを同時に知った

背景の記憶(235)
約束の場所の交差点は、多くの人々でごった返していた。
街灯の柱に寄っかるようにしていた君は、鮮やかな赤いタータンチェックのスカー
トを身に着けていた。
一瞬、周りがモノクロに変わり、赤いチェック柄が浮かび上がって見えた。
いつもはほとんど黒系統のファッションの君だから、余計にそう見えたのかもしれ
ない。
ストップモーションの風景が、せわしなく動き始め、僕は信号を渡り、素早く腕を
組んだ。
君を誰かに奪い去られないように・・・とでも言うように。

背景の記憶(232)
はにかむ君がいい
赤らめた頬がいい
拗ねて見せた横顔がいい
光る涙は本物だった
追いかけてきた君がいい
衝突を恐れない自転車に
君の本気を知った
必死に探す君がいい
曲がり角で身を隠した僕を
君は必死に探していた
僕を見つけた時の君がいい
僕の腕を抓る仕草が
ちょっと本気であどけなく可愛かった
忘年会の夜の君がいい
おめかしして別人のようだった
当然のように僕の隣に座ってくれた
電話の向こうの君がいい
携帯をonにして僕は歌った
歌詞に君への想いを重ねて・・・
透きとおる素肌の君がいい
男物のシャツの下に
僕は飛び上がるほど驚かされた
今はもう遠い
そう・・・遠い過去の想い出
でも、昨日のような鮮明さ

背景の記憶(230)
先 生
先生 ぼくは 先生の逆です
ゆうべに願い
あしたに空しく
崩れている自分です
それでいて
どう生きたい願いなのかと
考え考えしている自分です
先生 ぼくは 先生の逆です
ただ じっと待ってなどいられません
待っていれば向こうから歩いてござるなんて
決して決して
僕は追います 何にもなくても追います
追ったら負けだなんて
負けでも いいじゃないですか
先生 ぼくは 先生の逆です
一本の草花 一片の雲 一人一人の横顔一語一語・・・
ぼくにはそれそのものしか感じられません
あらゆる角度の目だなんて
ぼくにはそんな日がいつ来るのでしょう
先生 ぼくは 先生のようにできません
先生は日新にして日進と言われる
さらに月新にして月進でありたいと
先生には一歩退き それでいいのかそれでいいのかと
振り返る余裕がおありだ
ぼくには後ろが見えない
前方から吹き付ける風を
うつむいて こらえるのが精一杯
先生 ぼくは 先生の逆です
それでいい それでいいなんて
さりげなく さりげなくなんて
もっともっと欲しいんです
恋でもなんでも
自分のすべてを燃やしてぶつかるものが
先生 ぼくは なんでも先生の逆です
そこで先生はおっしゃりたいのでしょう
物にも事にも裏表二つの顔があるのだと
わかっているんです 先生のおっしゃることすべて
でもどうしても ああこれが人生なんだと
割り切れない 悟りきれないのです
それこそ本当の負け惜しみのような気がして
こうして何もかも反発しているのです
お許しください 先生
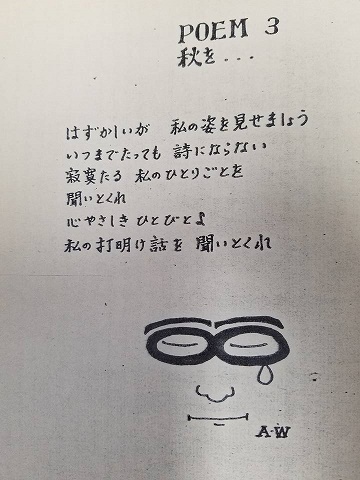
(50年前の手作り詩集)
背景の記憶(229)
中学一年生の国語の授業
永田先生はしなやかな(?)鞭を持っていた。
体罰は無かったと記憶しているが、黒板と言わず机と言わず・・・
ビシッ!ビシッ!とやられた。
まず最初にさせられたことは、国語辞典を左手で持ち、左手だけで
目的の語のページを瞬時に出すという特訓(?)だった。
両手を使っていたのでは、時間の無駄というわけだ。
もう一つは、助詞・助動詞の丸暗記
が の を に へ と から より で や ば と ても でも
けれども のに ので から して で ながら たり だり れる
られる せる させる
どちらも、今でもできちゃうんだから、この特訓はすごい。
父とは正反対の、眼光鋭いモーレツ先生だった。
背景の記憶(228)
生まれ故郷・隠岐の島の祖母から送ってもらった・・・お米と舐め味噌
味噌に飽きたら(勿体無い話だが)
醤油をかけて・・・
塩をまぶして・・・食べた
お米が無くなったら
一週間でも十日でも
水ばかり飲んでいた
氷屋さんのアイスキャンディーが欲しくて堪らなかった
でも・・・それを買う10円、20円が無かった
ほんとに〜お腹と背中がくっつくと思った
丸一日、いや二日でも・・・
畳の上で寝たままの時もあった
布団は無かった(冬でも)
・・・・・・・・・・・
「臥薪嘗胆」とは程遠い
遠い〜遠い昔の広島時代
暑い日の思い出

背景の記憶(227)
ボーイスカウトの訓育会でのこと
みんなを野外に集めて、目隠しの鬼ごっこゲームをやった。
鬼は目隠し、他のものは決められた円から外へは出られなかった。
捕まえた者の名前を当てるというゲームだったのだが・・・
何人目かの時に、僕が捕まった。
抵抗したつもりはなかったが、僕は高く持ち上げられ、そして落とされた。
草むらではあったが地面は固く、僕は運悪く後頭部をしこたま打ち付けた。
そこで意識を失った。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三日三晩、僕は昏睡状態だったらしい。
幸い意識は回復したが、その後かなりの年数〜偏頭痛に悩まされた。
ちょっと運動をすると、後頭部に重い石がひっついているようで
二十歳を過ぎてもずいぶん悩まされたものだ。

あのころ・・・
背景の記憶(226)
あの時、トンネルの出口だと思った
丸く鈍い光は幻だった
砂漠の中の蜃気楼のようなものか
いくつもの曲がり角や別れ道
ほとんど勘みたいなもので歩いてきたけど
これを選択ミスと言われるのかな
でも・・・
どんなに滅入ったって立ち直れるさ
立ち直ってみせるさ
たとえ絶望の淵からでも
デパートの地下二階のエレベーターの中で
庫内灯を消してみたあの時
冷気と暗闇が体を包み
地獄を垣間見たような気になった
呼び出しのランプに救われて
僕はその階へ上がって行った
