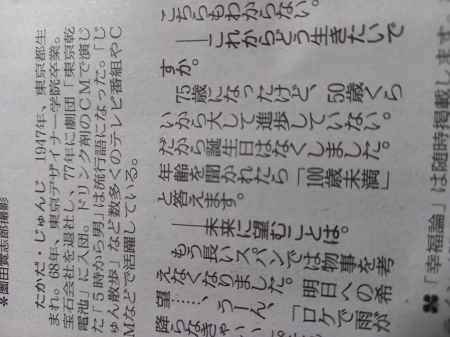背景の記憶(295)
湖の干拓地 車の通らない跨線橋
独りぼっちの街灯 夢の影
わずかな時間の 待ち合わせ
言葉はいらない
ただ寄り添い 手を握る
あの遠い日の涙は
明日への希望ではなかったのか

posted by わたなべあきお | - | -
背景の記憶(294)
高校二年の時、進学校の得体の知れない圧力に屈して、僕は登校拒否になった。自宅は出ても学校の近くのばあちゃんの家に行くようになった。ばあちゃんは問い詰めるようなことは一言も言わず、「カルタ(花札)しょうや」と言って遊んでくれた。僕にも分かるようなイカサマだったが、僕はそれもまた嬉しかった。あの数ヶ月が無かったら、僕は出口の無い暗闇に入り込んで行ったかも知れない。
posted by わたなべあきお | - | -
背景の記憶(293)
小学校の遠足の二三日前
汚れたズック(布靴)をタワシで懸命に洗った。
親にあれこれと買ってくれとは言いづらい時代だった。
昭和二十年代の話。
当時は、さすがに裸足というのは無かったが
平素はゴム草履か黒い短靴を履いていた。
どこの家も総じて貧しかったから、履物にそれほどの
執着は無かった。しかし、
大人ならよそ行きの服とか一張羅とかいう言葉が
存在する時代だったから、子供にもそれなりの意識はあった。
子供なりのよそ行き感覚だったんだろう。
徐々に異性を意識し始めて、体裁を考え出したということだろう。
実のところは、そんなひとの風体など気にはしていないのだが
子供なりの自意識というか、そんな感情が芽生える時期だった
のかもしれない。
posted by わたなべあきお | - | -