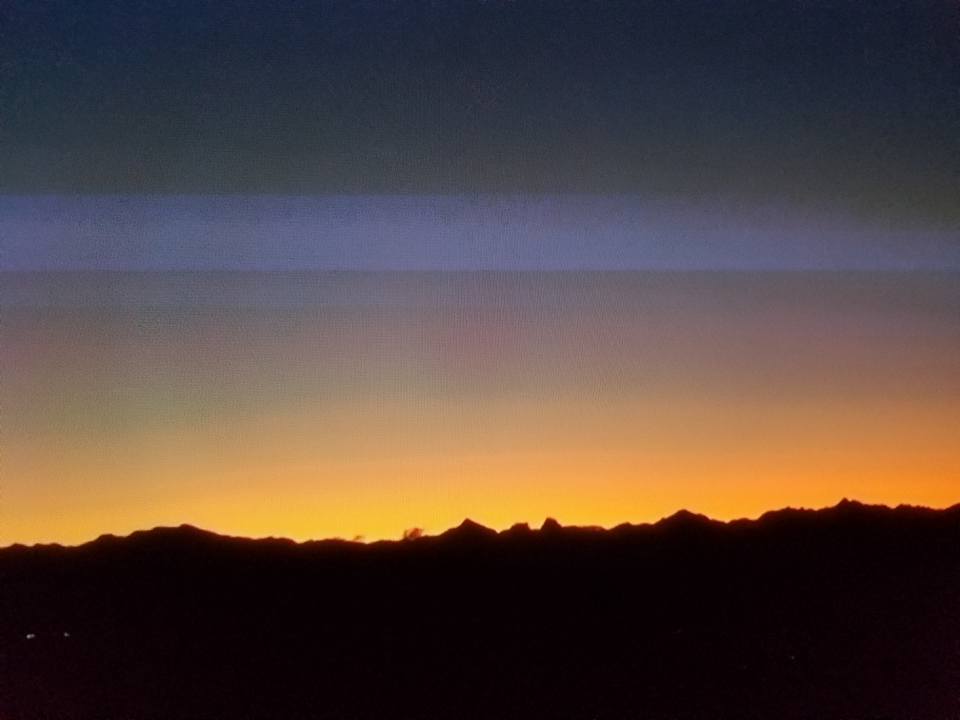逆境
・・・形のあるものは頼みにならない。
母はよくそう云っていた。金でも物でも、使えば減るか無くなってしまう、形のある物はいつか必ず無くなってしまうものだ。大切なのは減りもせず無くすこともできないものだ。人によってそれぞれ違うけれど、見つけようとすれば誰にでも、一つだけはそういうものがある筈だ。
「あなたの持っている才能も、このままではだめだ、もっと迷い、つまずき、幾十たびとなく転び、傷ついて血をながし、泥まみれなってからでなくては、本物にはならない」
「書物からまなぶ学問ではなく、生きた人間と、その生活です。人間と生活と、それを取り巻く世間、それが私の勉強の対象ですよ」
「人間にいちばん大切なのは逆境に立ったときだ、借銭などでいちじを凌ぐ癖がついたら、とうてい逆境からぬけ出ることはできない、どんなに苦しくとも、自分の力できりぬけてこそ立ち直れるものだ」
山本周五郎

一生
「おれは風が向うから吹いて来て、そして吹き去ってゆくのを感じていた、そのうちふと、いま自分に触れていった風には、二度と触れることはできない、ということを考えた、どんな方法をもちいても、いちど自分を吹き去っていった風には二度と触れることはできない・・・そう思ったとき、おれは胸を押しつぶされるような息苦しさ、自分だけが深い井戸の底にいるような、真っ暗な怖ろしさに圧倒された」
「たいせつなのは身分の高下や貧富の差だはない、人間と生まれてきて、生きたことが、自分にとってむだでなかった、世の中のためにも少しは役立ち、意義があった、そう自覚して死ぬことができるかどうかが問題だと思います。人間はいつかは必ず死にます、いかなる権勢も富も、人間を死から救うことはできません、そして、死ぬときには、少なくとも惜しまれる人間になるだけの仕事をしてゆきたいと思います」
「百姓も猟師も、八百屋も酒屋も、どんな職業も、絵を描くことより下でも上でもない、人間が働いて生きてゆくことは、職業のいかんを問わず、そのままで尊い、絵を描くということが、特別に意義をもつものではない、・・・私はこう思い当たったのです、わかりきったことのようですが、私は自分の躯で当ってみて、石を担ぎ、土運びをしてみてわかったのです、そうして、初めて本当に絵が描きたくなって帰ってきたのです」
山本周五郎

背景の記憶(240)
四人はいつも行動を共にした。僕のつけたあだ名は、スタローンにミックジャガーに猪八戒。風貌からしてこれ以外のあだ名は思いつかなかった。僕は何て呼ばれていたのだろう?あだ名を付けにくいほど、どこにでもいるようなヒッピー被れだった。
スタローンはほんとにそっくりだった。髪型も顔の堀の深さも体型も。ヘンリーミラーの分厚い本をいつも持ち歩いていた。広島のある新聞社の編集長の息子と言っていたけど、家出の理由は結局話さずじまいだった。ピアノの素養もないのに、バイト先のデパートの従業員休憩室で、いきなり無茶苦茶にたたき鳴らす行動をとったりして驚かせた。即興とも言えない、メロディーもなってない、ひたすら両手を鍵盤に叩き付けていた。「芸術は爆発だ!」岡本太郎を連想した。
ミックはすべてを真似ていた〜と言うか、なりきっていた。髪型、ファッション、歩き方・・・。バイトを終えたら必ず向かいの二階にある喫茶店に行った。ジュークボックスに小銭をつぎこんで、ストーンズの歌に酔いしれていた。目を瞑り足を鳴らし、自分だけの世界に浸っていた。
猪八戒は、これほどピッタリのあだ名はないほど酷似していた。ちょっとがに股で、動物のような歩き方をした。唯一自分の家から通っていた。僕と同じ姓だけど、彼は「ワタベ」だった。何がどう違うのか、いつからどうなったのか、姓の由来で長々と議論したこともあった。家の商売の跡を継ぐとか言っていた。袋帯か何かの関係と言っていたような・・・。
僕は家出息子には違いなかったが、冒険はできない小心者だったと思う。何事にも挑戦はしたが被れることはなかった。ヘアースタイルもファッションも当時の若者と何一つ変わらなかったが、中身とマッチングには?だった。異性にも臆病だし、いつもみんなの後を歩いていた。檻の中から急に解き放たれた小動物のように、世間に怯え、怖々と風の強さと冷たさに、懸命に馴染もうとしていた。
二十歳のエチュード。