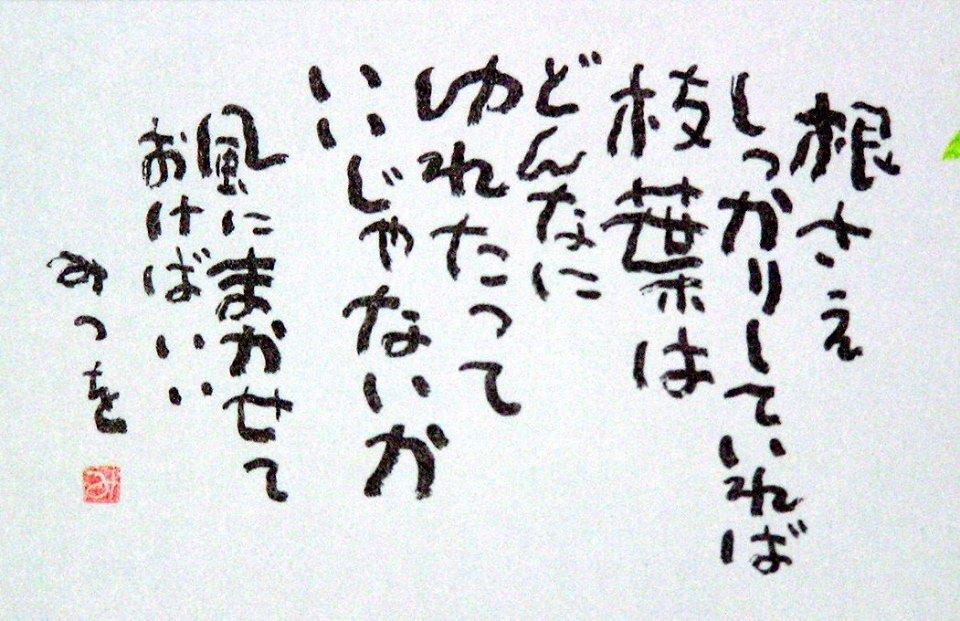背景の記憶(281)
「横顔が好きっちゃね〜!」
助手席の彼女がいきなりそう呟いた。
「えっ!?」
まさか・・・僕のこと?
とてもじゃないが顔に自信があるわけでもなく
からかわれているんだと思った。
でも、よく見るとそうでもない表情の彼女だったので
僕は照れ隠しもあって、車を発進させた。
彼女はまだ二十歳前、だけど職場では先輩であるわけで・・・
同じ課だったから、いろいろとアドバイスを受ける関係だった。
僕は自分で言うのも変だけど<波乱万丈>の少年時代、青春時代を
過ごしてきたわけで、一種の人間不信、女性不信に陥っていて
職種も人との言葉的関わりの少ない技術的な外現場仕事を望んで入社した。
仕事を終えて帰社したら日報を提出して「お先に失礼します」の毎日。
事務の彼女は、営業の社員に多く入る電話注文や事務連絡を快活にこなす
明るいマスコット的存在だった。当時はミニスカート全盛で、彼女もその
流行に後れることなく超ミニのスカートを穿いていた。言葉は古いが
トランジスタ的娘だったので、小学生のような振る舞いの時※※チラも
度々だった。
ある日のこと、僕の机の上にメモが貼り付けてあった。一枚目は業務連絡。
二枚目に「ちょっと相談に乗ってください」と言うのがあった。日報を渡す
時に、「OK」のメモを返した。このころには仕事にも慣れて、僕の人見知り
も随分改善されていたので、躊躇する材料は何もなかった。
会社からちょっと離れたところで彼女が車に乗り込んできた。さらにちょっと車を走らせた公園横に停車して「どうしたの?」と聴くと、「引っ越ししたいから手伝って欲しいの」彼女は寮で暮らしていたから、そろそろ自由になりたいとのことだった。そんなことなら〜というわけで僕は快諾した。そしてその後に発した言葉が「横顔が・・・」だったんだ。
でも、その時は深く受け止められず、異性への拒絶反応もぬぐい切れてはおらず極力深く考えないようにした。でもそれは彼女の心からすれば超反比例的な想いであったわけで・・・。
そもそも五歳年上の彼女との別離の経験者が、今度は五歳年下の彼女からの告知的ことばだったからね。即座には受け止められない自分がいた。
背景の記憶(280)
クラブの帰り道、僕は彼女よりちょっとだけ早く表へ出た。
彼女は自転車、僕は徒歩。最初の曲がり角まではゆっくり歩いて
曲がって彼女の視界から消えた時、音を立てずに走ってマンションの
塀の陰に隠れた。
すぐに追いつくだろうと思って角を曲がってきた彼女は、僕の姿がない
ので、辺りをキョロキョロしている様子だった。そして即座に猛烈な
勢いで自転車をこぎ始めた。僕の隠れてていた場所も瞬時に通り過ぎて
行ってしまった。
そのあまりのスピードに、僕はその先の衝突事故とかが心配になって
猛烈にダッシュして彼女を追いかけた。次の大通との十字路で、彼女は
左右を見まわして必死に僕の姿を探している様子だった。
僕はひとまず安心して、今度は忍び足で彼女に近づいて行った。
その気配に気づいた彼女は、振り向いて・・・心配と安ど感とがごっちゃに
なったような顔で僕を迎えた。そして、僕のイタズラに気が付いたらしく
今度は思いっきり頬を膨らませて「もう、赦さない!」と拗ねた顔をした。
「ゴメン、ゴメン!」と素直に謝って、二人並んでゆっくりゆっくり
歩き始めた。バス停が近づくころには彼女の機嫌も直っていて、素直に
バイバイすることができた。バスの中で、彼女のあの必死さというか
まっすぐさが嬉しくて、ひとりにやけている僕だった。